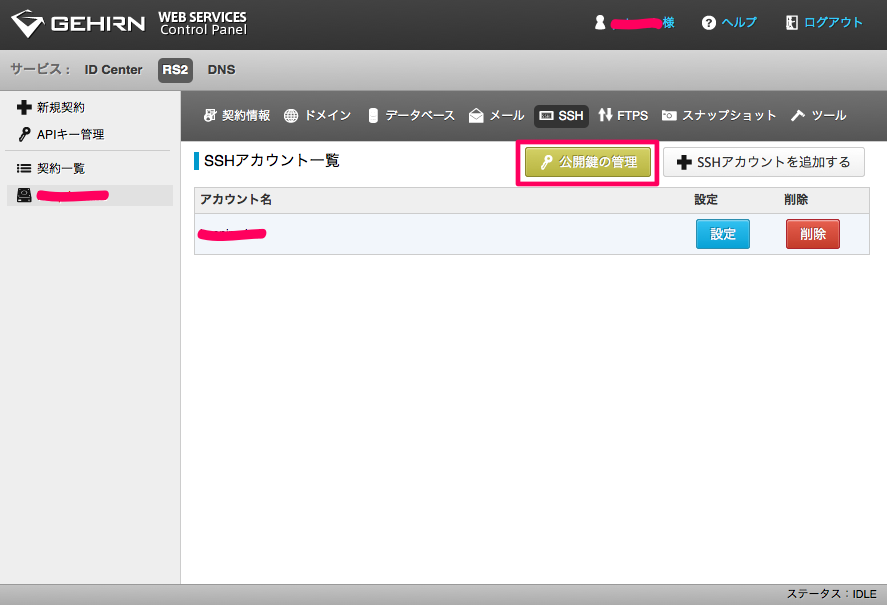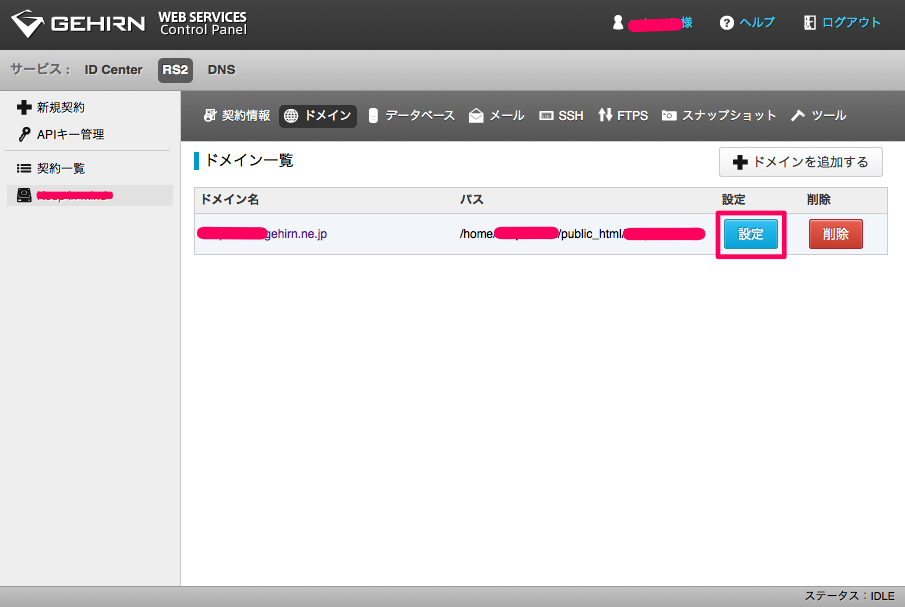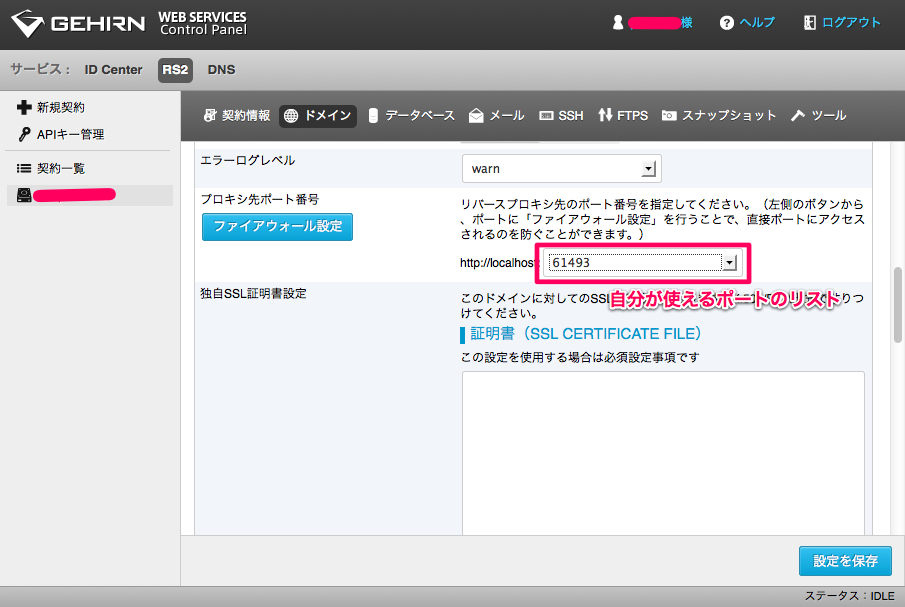電脳書房さんより、アジャイルな時間管理術 ポモドーロテクニック入門
を買ってみました。
一応全部読み終わったので、思ったことを書いていきます。
ポモドーロとは、イタリア語でトマトのことであり、ポモドーロテクニックとは、トマト型のキッチンタイマーを使って時間を区切って物事に取り組むことです。
別にトマト型のキッチンタイマーじゃなくてもできますが、筆者は機械的なトマト型のキッチンタイマーのほうが集中できるというふうに書いてました。時間を区切ることができればなんでもいいと思います。ケータイのタイマーでも全然いいでしょう。
やることは非常にシンプルで、
- やるべきことのリストを1枚の紙に書き出す。
- そこから優先順位を考えて、いくつかを今日やることリストに移す。
- タイマーを25分にセットして、リストの項目を1つずつ取り組む。
- タイマーが鳴ったら、5分くらい休憩する。
- 対象のToDoが終わったら、線を入れて終わったことがわかるようにする。
- それを繰り返す。
- 一日の終わりに、振り返りを行う。
振り返り云々はさておき、25分に区切って集中するというのはとてもいい方法だと思いました。人間の集中力は長くても30分程度しか持たないと思うし、頻繁に休憩を取り入れるほうが能率が上がるというのはなにかの本で読んだことがあります(カーネギーの本だったかな…)。
また、25分取り組むというのは何かを始めるいいきっかけになると思います。一度取り組み始めたら終わらせなければならない。そういうプレッシャーでなかなか始めることができない(完璧主義で)。そんなものはどっかに置いといて、とりあえず25分取り組んでみて、そこからフィードバックを得る。そのほうがずっと建設的だなと思います。
いいなと思った点としては、他にもあって、非常にアナログなのです。
準備するものは、
- 紙
- 鉛筆
- キッチンタイマー
だけです。特に上位2つはデジタル化できるんじゃないの?と思うかもしれません(私も読んでて思いました)が、本を読んでいる間に、こういうのはアナログなほうがすぐに始められるし、ルールに縛り付けられなくて済むんじゃないかなと思うようになりました。特に、割り込みが発生したときに、すぐに対応できるのはやっぱり紙だなと思いますし。もちろんデジタルではできないという意味ではないです。デジタル向きか、アナログ向きかと言われたら、アナログ向きだという意味です。
本には、序盤にポモドーロテクニックの紹介、取り組み方、ルールの替え方、振り返りの仕方、休憩の仕方、割り込みへの対応の仕方(内なる割り込み・外的割り込み)、チームでやるには?ということについて書かれています。アジャイルな時間管理術という副題が付いていますが、1人アジャイルに向いている考え方だなと思います。イテレーションを回すのに、期間は基本2週間で、それぞれのToDoのベロシティを計測するという感じだと思うのですが(ペロシティとは、項目に対してかかるコストの単位)、ポモドーロテクニックだともっと短くて、期間は1日で、それぞれのToDoのポモドーロを計測します(ポモドーロは、基本25分の固まり)。
人の見積もりの精度は、経験則に依存しています。また、ToDoのコストが短ければ短いほど、見積もりは正確になります。その精度を上げる意味でも、自分が見積もった項目が何ポモドーロかかったのか?を計測し、その見積もりに対しての振り返りを行います。自分のできる能力の把握し、今後の予定の立て方に活かすことができるようになります。
意外だったのが、休憩の仕方のところで、休憩のときにメールの返信やニュースサイトのチェックを行うのがよいと思っていたのですが(気分が切り替わってていいのかなと…)、それだとストレスがあって本当の休憩にならないから、そういうのはToDoに入れてしまえというところでした。
自分が一日に何ポモドーロ取り組むことができて、どれくらいのことをこなすことができるのか。それを把握するのが大事だなと思います。
あとはやはりToDoリストをどんどん倒していけるという楽しさがあるかなと思います。特に何をしていたのかよくわからないまま、一日が終わってしまったということがないよう、振り返りを行いつつ、ポモドーロテクニックを習慣化していきたいところです。